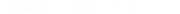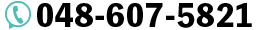偉人伝 李光耀 ③#53
首相となった李光耀の前には、解決しなければならない問題が山のように積み上がっていました。その1つひとつに、誠実に対応していきます。
まず、独立国としての認識を世界に広げたいという目的から1965年に国際連合に加盟、そして1967年に東南アジア諸国連合(ASEAN)を設立しました。インドネシアと良好な関係を築き、シンガポール人としての文化、ナショナリズムを作ることに力を入れていきます。
経済政策については早急に取り組まなければならず、イギリスから独立したことにより失った、10万人とも言われる雇用の喪失を取り戻す必要がありました。しかしながら地場産業を持たないシンガポールの雇用はなかなか良くなりませんでした。
そこで経済特区を作り出し、外国の企業を積極的に誘致し輸出志向型の工業化戦略を打ち立てます。税制面でとても優遇されたこの地に、当時世界最先端の技術を持つ企業が次々と参入しました。と同時に、政府は経済の厳重な統制を維持し、土地と労働、資本的資源の配分を管理しました。ようするに外国資本に好きなようにはさせないように管理をしていたのです。
この政策が軌道に乗り始めると安定した経済成長を遂げ、インフラも急激に整備されていきます。
そして観光にも力を入れ、外国人観光客を誘致するために観光局を設立しました。徹底的なクリーン政策もその一環であると言えます。「東南アジアは衛生面で問題がある」というイメージを一掃することに成功しました。その結果、サービス産業で多くの雇用を創出することができました。観光はシンガポールにとって重要な外貨獲得の手段の一つとなっていきます。
この取り組みは、世界でも注目を浴び、たくさんの政治家、経営者がシンガポールに学びにやってくるようになりました。中国民主化の父とも言われる鄧小平氏もその名を連ねています。当然ながらシンガポールの雇用は劇的に回復し、今や世界有数の経済大国であることは知っての通りです。
シンガポールでは、英語で授業がなされてはいますがマレー語、タミル語も公用語として認め、ここにもナショナリズム獲得のための取り組みを見ることができます。教育にもとても力を入れ、自身が学んだラッフルズ大学はシンガポール国立大学と名前を変え、清華大学がトップになる以前はアジアで1番の大学として名を馳せていました。
汚職が国家を滅亡させるという信念を持ち、徹底的にクリーンな政治を標榜しました。実際に数多くの大臣が逮捕、失職という目に遭っています。まさに国家の地位向上に全精力を注いだ、真の政治家と言えるのではないでしょうか。
独裁政権と聞くと、なんとなくマイナスなイメージを持ちますが、こういう形もあるんだと、とても感銘しました。体調不良で任期を全うすることができず、そしてその直後に水面下では次期首相が決まっているという、なんともクリーンなイメージを持つことの難しい今の日本に、李光耀のような人物が登場してくれることを願うばかりです。