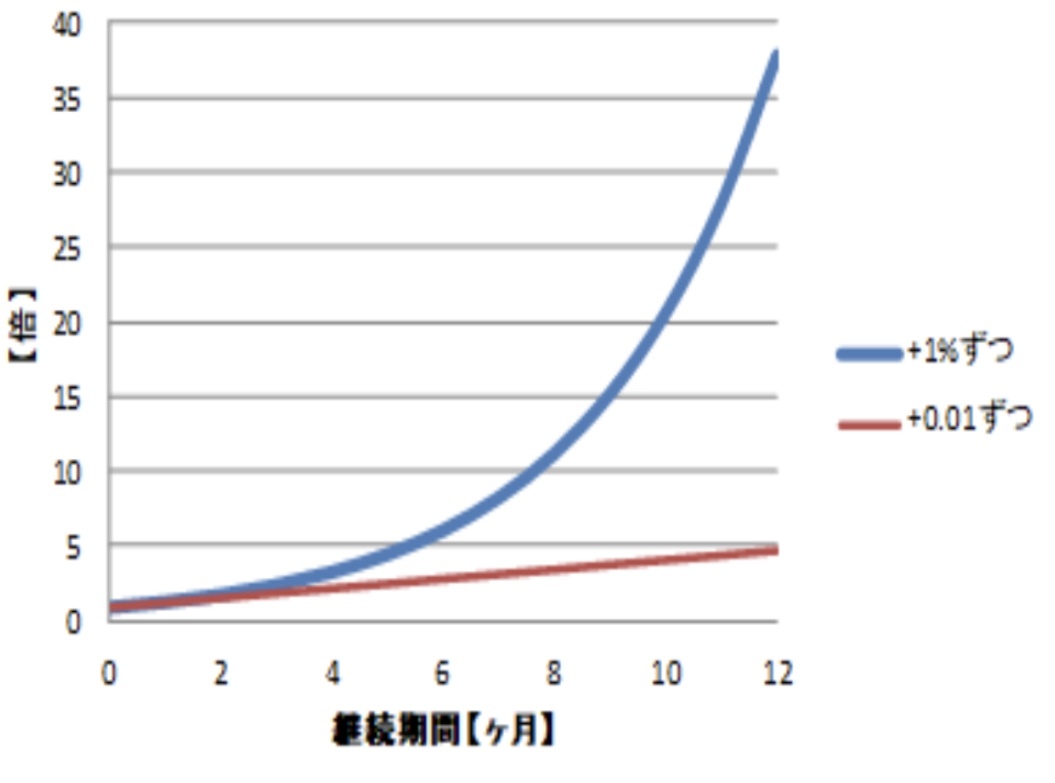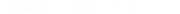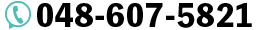論語②#22
前回から引き続き、論語の言葉の解説をしていきます。
■これを知るをこれを知るとなし、知らざるを知らざるとなせ。これ知るなり。
現代語訳:知っていることは知っている、知らないことは知らないとする。それこそが「知る」ということだ。
(補足)知ったかぶりをやめて、知らないことは「知らない」と言うことが、真の「知る」ことだと言っています。「無知の知」ともつながる言葉ですね。
■学んで思わざればすなわち罔(くら)し。思うて学ばざればすなわち殆(あやう)し
現代語訳:学んでも思考しなければどう活かしたらいいのかが分からない 思考してしてばかりで学ばなければ危険である
(補足)多くの中学校の教科書にも掲載されていること文ですが、意味をとるのに苦労した経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。これは、知識や情報は自分の頭で整理して考えないと、本当に役立つものにはならない。また、一人で考えても情報を得なければ、懸命な判断ができず独善的になってしまう。
「学ぶこと」と「考えること」はどちらに偏ってもいけなくて、両方を行っていきなさいということです。
■故(ふる)きを温めて新しきを知る、もって師となるべし
現代語訳:古いことをよく探求して現代に応用できるものを知っていく そういう人こそ人の師になれる
(補足)あまりにも有名なこの一節。「温故知新(おんこちしん)」という四字熟語にもなっている言葉ですね。いま正に『論語』を学ぶ私たちにも言える言葉です。
■吾(わ)れ十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑(まど)わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順(した)がう。七十にして心の欲する所に従って、矩(のり)をこえず
現代語訳:私は15歳で学問を志し、30歳で独立した立場を持った。40歳であれこれ迷うことがなくなった。50歳の時に天から与えられた使命を知った。60歳になって誰の言うことでも反発せず聞けるようになった。70歳になると自分の思うままにふるまっても、道を踏み外すことはなくなった。
(補足)孔子は74歳まで生き、晩年に自分の一生を振り返った言葉だと言われています。当時としては稀に見る長寿であり、平均寿命の延びた現代にそのまま当てはめることは難しいのですが、人の一生を考える参考になります。
この論語から、15歳を志学(しがく)、30歳を而立(じりつ)、40歳を不惑(ふわく)、50歳を知命(ちめい)、60歳を耳従(じじゅん)、70歳を従心(じゅうしん)という言葉が作られました。
■義を見てせざるは勇なきなり
現代語訳:人として行うべきことを知っているにもかかわらず、できないのは勇気が足りないからだ
(補足)正しいことでも行動を起こすには勇気が必要です。勇気が足りないことに気付かせ、行動を起こすように促す励ましの言葉でもあります。
■君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
現代語訳:賢い人は人と調和するが安易に同意はしない 愚かな人は意見がなく流されるが協調性はない。
■過ぎたるはなお及ばざるがごとし
現代語訳:行き過ぎは足りないのと同じようなことだ。
(補足)バランス良く適切に物事を行いましょう。やり過ぎもよくないですよ、という教えです。
■益者三友、損者三友
現代語訳:自分にとって益になる友達が三種類、害になる友達が三種類いる。
(補足)益になる友達とは、「まっすぐ正直な人」、「誠実な人」、「博識な人」のことです。
一方、害なる友達とは、「体裁だけを取り繕う人」「人当たりはいいが誠実でない人」「口先だけ上手い人」のことを指します。
友人は慎重に選ぶべきだという意味が込められています。
■益者三楽、損者三楽
現代語訳:自分にとって有益な楽しみが三種類、損をする楽しみが三種類ある。
(補足)有益な楽しみとは「礼儀、音楽を適度に楽しむ」「人の美点を話題にすることを楽しむ」「優れた友達の多いこと楽しむ」ことです。
損をする楽しみとは「おごりわがままに楽しむ」「怠け遊ぶことを楽しむ」「酒を飲んで騒いで楽しむ」ことだと述べています。
今回紹介したのは『論語』の一部で、この他にもまだまだ数多くの名言があります。
論語には、学習や人付き合い、親子関係や老後についてなどを記した語が散りばめられています。「仁」という思いやりの心、「義」という道理に適うこと、「礼」を忘れないこと、「智」恵を備えてわきまえること、「忠」という真心、「信」頼されるよう誠実であること、「孝」行することが大切だと述べられています。この中でも特に重要視されたのが、「仁」と「礼」です。
「論語」には、現代人も学ぶべきところがたくさんあります。紀元前にこのような思想がすでにあったということに、改めて驚いてしまいました。
2020年06月20日 14:20